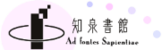ホーム > デカルトの知性主義
目次
略記号
はじめに
序章 哲学者研究の哲学
序
1 社会思想史説
2 科学者vs. 形而上学者
3 解釈の実在論――哲学的経験としての哲学
4 経験か体系か――科学・芸術・形而上学
5 マリオン説――解釈の否定神学論,ないしは「存在–神–論」のプリズム
結
第Ⅰ部 方法
第1章 方法の誕生――方法の新たな精神化の歴史
序
1 自由七科の消失と論証法としての論理学(dialectica)
2 自由七科としての論理学と論理学の起源
3 方法への意志――弁証的方法・普遍的理性
結
参考資料
第2章 数学のモデル――数学的方法と方法の精神
序
1 デカルト以前の数学的記号と普遍数学
2 デカルトの数学的方法の方法化
結
第3章 推論と理性――デカルトの三段論法批判から形而上学の方法へ
序
1 外延説
2 形式説
3 数学モデル
結
第Ⅰ部 結論
第Ⅱ部 懐疑
第4章 作者の発作ないしは方法の危機
序
1 「蒸気」の歴史
2 作者の発作,もしくは作者の危機
結
第5章 精神を感覚から引き離すこと――トマスの抽象とデカルトの懐疑
序
1 数学の懐疑をめぐる諸見解
2 トマスの抽象
3 デカルトの数学の懐疑
4 デカルト的理性の誕生
結
第Ⅱ部 結論
第Ⅲ部 コギトとエゴの存在
第6章 『規則論』における“Ego sum”と“Ego cogito”の順序関係について
序
1 直観(intuitus)と導出(deductio)
2 セールによる順序
3 セール説の検討と展開
4 形而上学
結
第7章 ソクラテス的反転――ドゥビトの確実性からスムの必然性へ
序
1 コギト・エルゴ・スム推論説
2 コギトを条件とするスムの必然性
3 ドゥビトからコギトの確実性へ
4 ヒンティカのパフォーマンス説
結
第8章 エゴの持続と観念の永続
序
1 観念と時間
2 懐疑の病から〈コギト・エルゴ・スム〉の瞬問の復帰へ
3 エゴの同一性
結
第Ⅲ巻 結論
第Ⅳ部 デカルト形而上学の構造
第9章 方法と第一哲学――エゴの覚醒とコギトの論理構造の展開
序
1 第一哲学における方法
2 単純本性と第一哲学
3 コギトの論理構造とその確証
4 精神と知性
結
第10章 知性弁護論――反意志主義的解釈の試み
序
1 「第四省察」をめぐる諸見解
2 能力論としての「第四省察」と意志主義神話の崩壊
結
第11章 デカルトの循環――失われた記憶を求めて
序
1 記憶説の陰り,もしくは明証性の画一性
2 仮説演繹法,もしくは失われた記憶
3 永遠真理創造説,もしくは本質の不変性
4 神の存在証明,もしくは宝庫の発見
結
第Ⅳ部 結論
終章 「欲求」(appétit)の左遷
序
1 デカルト周辺の情念規定とトマス・アクィナスの欲求の存在論
2 デカルトにおける機械論的かつ記号論的な情念
結
全体の結論
あとがき
参考文献
人名索引
事項索引
はじめに
序章 哲学者研究の哲学
序
1 社会思想史説
2 科学者vs. 形而上学者
3 解釈の実在論――哲学的経験としての哲学
4 経験か体系か――科学・芸術・形而上学
5 マリオン説――解釈の否定神学論,ないしは「存在–神–論」のプリズム
結
第Ⅰ部 方法
第1章 方法の誕生――方法の新たな精神化の歴史
序
1 自由七科の消失と論証法としての論理学(dialectica)
2 自由七科としての論理学と論理学の起源
3 方法への意志――弁証的方法・普遍的理性
結
参考資料
第2章 数学のモデル――数学的方法と方法の精神
序
1 デカルト以前の数学的記号と普遍数学
2 デカルトの数学的方法の方法化
結
第3章 推論と理性――デカルトの三段論法批判から形而上学の方法へ
序
1 外延説
2 形式説
3 数学モデル
結
第Ⅰ部 結論
第Ⅱ部 懐疑
第4章 作者の発作ないしは方法の危機
序
1 「蒸気」の歴史
2 作者の発作,もしくは作者の危機
結
第5章 精神を感覚から引き離すこと――トマスの抽象とデカルトの懐疑
序
1 数学の懐疑をめぐる諸見解
2 トマスの抽象
3 デカルトの数学の懐疑
4 デカルト的理性の誕生
結
第Ⅱ部 結論
第Ⅲ部 コギトとエゴの存在
第6章 『規則論』における“Ego sum”と“Ego cogito”の順序関係について
序
1 直観(intuitus)と導出(deductio)
2 セールによる順序
3 セール説の検討と展開
4 形而上学
結
第7章 ソクラテス的反転――ドゥビトの確実性からスムの必然性へ
序
1 コギト・エルゴ・スム推論説
2 コギトを条件とするスムの必然性
3 ドゥビトからコギトの確実性へ
4 ヒンティカのパフォーマンス説
結
第8章 エゴの持続と観念の永続
序
1 観念と時間
2 懐疑の病から〈コギト・エルゴ・スム〉の瞬問の復帰へ
3 エゴの同一性
結
第Ⅲ巻 結論
第Ⅳ部 デカルト形而上学の構造
第9章 方法と第一哲学――エゴの覚醒とコギトの論理構造の展開
序
1 第一哲学における方法
2 単純本性と第一哲学
3 コギトの論理構造とその確証
4 精神と知性
結
第10章 知性弁護論――反意志主義的解釈の試み
序
1 「第四省察」をめぐる諸見解
2 能力論としての「第四省察」と意志主義神話の崩壊
結
第11章 デカルトの循環――失われた記憶を求めて
序
1 記憶説の陰り,もしくは明証性の画一性
2 仮説演繹法,もしくは失われた記憶
3 永遠真理創造説,もしくは本質の不変性
4 神の存在証明,もしくは宝庫の発見
結
第Ⅳ部 結論
終章 「欲求」(appétit)の左遷
序
1 デカルト周辺の情念規定とトマス・アクィナスの欲求の存在論
2 デカルトにおける機械論的かつ記号論的な情念
結
全体の結論
あとがき
参考文献
人名索引
事項索引
内容説明
デカルトは「近代哲学の父」と言われるが,それはなぜであろうか。「コギト」という近代哲学の原理を打ち立て,近代科学を産み出す幾何学的方法の発見,前時代の学を根本的に壊滅させ,物体の本質を延長とみなす機械論的科学論などがその理由である。しかし現代においてヨーロッパ哲学はデカルト哲学というアイデンティティを失い自己喪失に陥っている。本書はデカルト研究を通して再び「哲学すること」を問いかける。
第Ⅰ部では,まずプラトンからベイコンへ至る方法論の歴史をたどり,その上でデカルトが見出した,既知の規則に縛られることのない,精神を未知の問題解決の極意へと導く,数学をモデルとした普遍学の「方法」の純粋で単純な性質を提示する。
第Ⅱ部では,方法に則った「懐疑」の意図とその対象,妥当性を考察する。デカルトの懐疑が,既存の知を疑い,新たな形而上学の原理を発見し,さらにそれを基に機械論的な自然学への途を開く。
第Ⅲ部では,真に疑えないもの「コギト」が見出される過程を追う。〈コギト・エルゴ・スム(私は思惟する,それゆえ,私はある)〉の内部構造と方法主体「エゴ」の分析的方法に支えられたあり方を見ていく。
第Ⅳ部では,第一哲学(存在論)と方法,さらに第一哲学の方法の主体を掘り下げる。デカルト形而上学の知性弁護論的性格や,方法と第一哲学との互いに基づけ合う循環構造といった仕組みが明らかとなる。
本書はデカルト研究,哲学史研究を,たんなる対象研究に終わらせるのではなく,自らの「哲学の実践」とすることを示した労作。
第Ⅰ部では,まずプラトンからベイコンへ至る方法論の歴史をたどり,その上でデカルトが見出した,既知の規則に縛られることのない,精神を未知の問題解決の極意へと導く,数学をモデルとした普遍学の「方法」の純粋で単純な性質を提示する。
第Ⅱ部では,方法に則った「懐疑」の意図とその対象,妥当性を考察する。デカルトの懐疑が,既存の知を疑い,新たな形而上学の原理を発見し,さらにそれを基に機械論的な自然学への途を開く。
第Ⅲ部では,真に疑えないもの「コギト」が見出される過程を追う。〈コギト・エルゴ・スム(私は思惟する,それゆえ,私はある)〉の内部構造と方法主体「エゴ」の分析的方法に支えられたあり方を見ていく。
第Ⅳ部では,第一哲学(存在論)と方法,さらに第一哲学の方法の主体を掘り下げる。デカルト形而上学の知性弁護論的性格や,方法と第一哲学との互いに基づけ合う循環構造といった仕組みが明らかとなる。
本書はデカルト研究,哲学史研究を,たんなる対象研究に終わらせるのではなく,自らの「哲学の実践」とすることを示した労作。